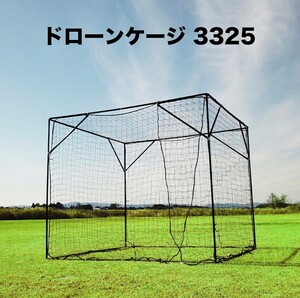GNSS連続観測点それぞれの違い
DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!
RTK測位でドローンを飛行させる際、どのサービス業者を選定しようとなるのですが、各企業のサイトに「独自基準点」「電子基準点」「民間等電子基準点」などいろいろな基準点が出てきており、それぞれ特徴はどんなものなのかを確認していければと思います。
電子基準点
全国約1,300か所に設置されたGNSS連続観測点です。電子基準点は、国土地理院が管理する国家基準点の1つであり、我が国の位置の基準である「国家座標」に整合します。外観は高さ5mほどのステンレス製ピラーで、上部にGNSS衛星からの電波を受信するアンテナ、内部には受信機と通信用機器等が格納されています。 基礎部には、電子基準点付属標と呼ばれる金属標が設置されており、トータルステーション等を用いる基準点として測量にも利用できるようになっています。

引用:国土交通省 国土地理院 電子基準点とはhttps://www.gsi.go.jp/denshi/denshi_about_GEONET-CORS.html
独自基準点
国土地理院の電子基準点とは別に、民間企業が自社で設置した高精度測位用の基準点のことです。例えば、ソフトバンクの提供するichimillは全国に約3,300か所の独自基準点を設置しており、これらの基準点からデータを取得・通信が可能です。
電子基準点との違いとして、国ではなく民間団体が設置している独自の基準点という点です。より高密度に整備される傾向にあり、精度が必要なICT施工などで有用ですが、日本測量協会の認定サービスではないため、公共測量などにおいては使用できません。
民間等電子基準点
国土地理院は、全国約1,300か所に設置された電子基準点と中央局から成るGNSS連続観測システムを20年以上運用し、 信頼性の高い観測データ及び測位結果を安定的に提供しています。 一方で、近年、スマート農業等で民間等によるGNSS連続観測局が設置され始めています。 GNSS連続観測局は位置情報サービスの要であり、もし設置者ごとに規格や準拠座標系が異なる場合、 利用者に混乱を与えてしまう可能性があります。そこで、国土地理院では、民間等のGNSS連続観測局の性能を評価し、 級別に登録する制度として、令和元年10月に「民間等電子基準点の性能基準及び登録要領」を制定しました。 国土地理院に登録された民間等電子基準点を利用していただくことで、国家座標に準拠し、 一定精度を有するGNSSデータを利用することが可能となります 。
引用;国土交通省 国土地理院 民間等電子基準点とはhttps://www.gsi.go.jp/eiseisokuchi/eiseisokuchi41030.html
それぞれ特徴が異なりますがご相談などがございましたら深空会社へお問い合わせください!